
人口が減少の一途をたどり続け、消費支出が確実に縮小していく。そんな切ない未来しかないこの国において、越境ECが海外の消費者に商品を販売できる新たな販路として見つかり始めています。そこで
「越境ECって何?」
「メリットやデメリットは?」
「どうやって始めればいいの?」
なんていう疑問がわいてきた方も多いのではないでしょうか。実際、越境ECは複雑で難しそうに感じるかもしれません。しかし、適切な知識さえあれば、越境ECは中小企業にも十分に取り組める販売方法。
要は学ぶか学ばないか、やるかやらないか、です。
越境ECとは? その3つの特徴

越境ECとは、海外の消費者に商品を販売するビジネスモデルのことです。もっと簡単に言うと、海外向けショッピングサイトの運営ってことです。インターネットって便利ですね。
実際には言語や文化の違い、法律や税金の問題など、考えるべきことがたくさんあったりしますが、そこをクリアできれば中小企業でも海外でブレイクなんてのが現実になるかもしれません。
とりあえず基本として、越境ECの3つの特徴を見ていきましょう。
国境を越えて、つまり海外に商品を販売するというビジネスモデル
越境とは文字の通り「国境を越える」ってこと。日本から、海外の消費者に「直接」商品を販売します。例えば、東京で作られた手作りの雑貨が、ニューヨークの誰かの部屋に飾られるってことです。
ただそんなこと、これまでだって当たり前に行われてきたはず。海外の大きな街には、日本の物が売られている店は普通にあります。
しかし従来の輸出との違いは、中間業者を挟まずに買いたい人と直で取引できること。買う人も店に行くことなく「検索」をして商品に出会えることです。要はネット通販を本腰を入れて海外向けに展開するってことですね。
今の自社ECサイトや大手モールも活用できる
越境ECを始めるからつって、新しくECサイトを作る必要はありません。今ある既存の自社ECサイトを活用したり、大手のECモールに出店したりすることでも、海外販売を始められます。
ちなみに自社のECサイトを使う場合は、以下の点に注意。
- 多言語対応:海外の顧客が理解できる言語でサイトを表示します。なんと日本以外の国では、まず日本語が通じません。
- 決済システムの整備:海外の主要な決済方法に対応する。まあ今は、クレカの他PayPalなんかの第三者支払いサービスなど便利なものがいっぱいあります。
- 配送方法の確立:国際配送の仕組みを整える。ヤマトや佐川、日本郵便、DHLなどがあるので、それぞれの特徴を調べとけばOK。
- 現地の法律への対応:各国の規制や税制に合わせる。ニセモノとか売ると、たぶんほとんどの国で面倒なことになります。
一方、大手ECモールを利用する場合のメリットは:
- 集客力:すでに多くの海外ユーザーが利用中
- 信頼性:大手モールのブランド力で安心感を与えられる
- システムの充実:決済や配送のシステムが整っている
- サポート体制:海外展開のノウハウを提供してくれることも
もちろん便利な分、手数料がしっかりかかるわけで、どちらを選ぶかは自社の状況や目標によって変わってきます。
為替リスクや言語対応がちょい面倒だけど重要なポイント
越境ECの課題で特に気をつけたいのが、為替リスクと言語対応です。これらは「ちょい面倒」と書きましたが、実際はかなり重要なポインツ。
学校で習ったかと思いますが、為替リスクについては円高や円安の影響を直接受けることになります。例えば、円高になると海外での販売価格が上がってしまい、競争力が落ちてしまう可能性が。
それと、言語対応も大切。商品説明や顧客対応を、相手国の言語で行う必要があります。ただ単純に翻訳するだけでなく、文化的な違いにも気使ってコミュニケーションしなければならない。
これらの課題は面倒に感じるかもしれませんが、面倒を乗り越えるからこそお金がいただけます。しっかり対策を立てることが、海外市場での成功につながるのです。
以下で越境ECのメリットとデメリットを、もうちょっとだけ掘り下げて見ていきましょう。
越境ECのメリットとデメリット5選

これから紹介する5つのポイントを押さえておけば、越境ECを始めるかどうかの判断材料になるはずではないでしょうか。
- 参入障壁が低い
- 24時間365日オープン!
- 在庫のリスクを抑えられる
- 言語や法規制の壁がある
- 配送コストと時間がかかる
メリット1:参入障壁が低い
最大のメリットは、市場に簡単に参入できること。
だって、まず物理的な店舗を海外に構える必要がありません。店がないので現地のスタッフを雇う必要もなく、人件費も不要になります。国内に事務所みたいなものがあれば、それで無問題。
さらに、小規模から始められるのも魅力です。大量の在庫を抱えて途方に暮れたり、人間関係を壊すような無理な借金で大規模な投資をしたりする必要がないんです。自社の状況に合わせて、小さな一歩から海外展開を進められるんです。
例えば焼き物織り物塗り物など、日本の伝統工芸品を作っている小さな工房でも越境ECを使えば世界中の人に商品を届けられます。
メリット2:24時間365日オープン!
時間や場所の制約がありません。文字通り24時間365日、世界中から注文を受け付けることができます。
例えば、東京が真夜中1時でもハバナでは昼の11時。ベルリンは夕方5時です。つまり、こっちが寝ている間でも商品が売れているかもしれないんです。寝ててお金が入るなんて、夢と間違えそうな状況ではないでしょうか。
もちろん、同時に24時間体制の顧客サポートが必要になる可能性もありますが、日本ほどのクレーム大国はほとんどありませんので、ちょっとくらい遅くなっても誠実に対応すればたいてい大丈夫のようです。
メリット3:在庫のリスクを抑えられる
越境ECでは、在庫のリスクを大幅に減らせます。注文が入ってから商品を発送すればいいんです。特にAマゾンさんの真似なんかできないという小規模事業者にとって、とても大きなメリット。
ただ、以上のメリットたちは、国内ECでもほぼ同じですね。商圏が広がるってことが越境としての最大のメリットですね。
デメリット1:言語や法規制の壁がある
デメリット1つめ、言語の壁と法規制の問題。
まず、商品説明や顧客対応を、その国の言語で行う必要があります。「DeepLとかG翻訳使えば簡単だろ」と思うかもですが、単に機械翻訳を使うだけでは不十分。その国の文化や慣習などの背景にも気を使わなければなりません。
例えば、日本語で「お手軽」という表現を英語に「直訳」すると、品質が悪いというイメージを与えかねません。こういった細かい表現にも気を配る必要があるんです。
あと、法規制の問題も重要です。各国にはそれぞれ独自の法律があって、従わないと大変なことに。例えばEUには個人情報保護法(GDPR)という厳しい規制があるんですが、これに違反すると多額の罰金を科されたりされなかったりという。
こういった言語や法規制の問題に対処するには、 翻訳専門業者や海外ビジネスの法務を扱っている法律事務所など、専門家のアドバイスを受けるのが良いでしょう。そこはなんとかケチらずに彼らの協力も得ながらクリアできれば、それ以上に大きな利益を得られるチャンスが待っているはず。
デメリット2:配送コストと時間がかかる
越境ECで避けられない課題2つめが、配送。国内配送に比べて、輸送費のほか関税などコストも時間もかかってしまいます。
配送に関する主な課題は以下の通り
- 高い配送コスト:国際配送は国内配送より高額になりがち
- 長い配送時間:場合によっては1週間以上かかることも
- 通関手続きの複雑さ:国によって異なる規制や税金への対応が必要
- 返品対応の難しさ:国際返品は手続きが複雑で費用もかかる
- 商品の破損リスク:長距離輸送による商品破損のリスクが高まる
これらの対策としては、
- 複数の配送業者を比較し、最適なサービスを選ぶ
- 配送料を商品価格に含める、または一定金額以上の注文で送料無料にする
- 通関手続きを代行してくれるサービスを利用する
- 返品ポリシーを明確にし、顧客に事前に理解してもらう
- 商品の梱包方法を工夫し、破損リスクを減らす
海外へ配送してくれるのは、佐川、ヤマト、日本郵便のほか、DHL、FedEx、UPSなどいろいろありますので、全部比較して試して自社にもっとも合った業者を頼むのがいいでしょう。
越境ECを始める際の4つの準備ステップ
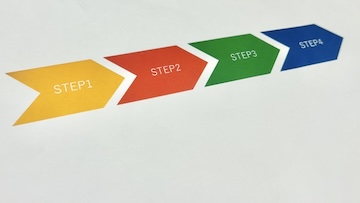
ステップ1:ターゲットとする国の選定と、市場調査
まずは、選んだ国によって戦略が大きく変わってくるので、どの国をターゲットにするかを決めましょう。
自社の商品は、どの国でモテそうなのか調査します。例えば日本の美容製品はアジア圏で人気があるみたいですが、こういった情報はネットで簡単に調べられます。
次に、その国の経済状況やECの普及率を調べましょう。経済が成長している国やECの利用率が高い国は、狙い目です。
あと、同業他社の状況も気にします。自分のところの商品と似たようなものを扱う会社がいっぱいあれば、違いを見つけるなり作るなりしてアピールしなきゃなりませんし、まだ参入者が少ないような市場なら大きなチャンスかもです。
ステップ2:販売チャネルの選択
ターゲット国が決まったら、次は販売チャネル選び。大きく分けて自社のECサイトを使う方法と、既存の大手ECモールに出店する方法があります。例えるなら路面に一戸建ての店を出すか、イオンに入るかって感じ。それぞれに良い点と厳しい点があります。
まず自社ECサイトを使う場合は、ブランドイメージを自由に作れる点が魅力です。ただし集客や決済システムの構築など、最初にやることがいっぱい。ただし、専門知識なくても作れるサービスもいっぱい。
一方、大手ECモールを利用すると、すでにある程度の集客が見込めます。AmazonやeBayなどといった世界的に有名なモールなら、信頼性も高いですよね。ただし、他の出品者との競争が激しくなる可能性がありますが。
まぁ、どちらを選ぶにしても、まずは小さく始めて徐々に拡大していくのがおすすめです。例えば、最初は大手モールで経験を積んでから、自社サイトを立ち上げるという方法もアリでしょう。
また、複数のチャネルを組み合わせるのも良い戦略です。もちろん手はかかりますが、自社サイトと大手モールの両方で販売すればリスク分散できますし、より多くの顧客にリーチできる可能性も高まります。
ステップ3:決済の方法と配送方法の確立
越境ECで成功するには、海外のユーザーがラクに簡単にストレスなく買い物できる環境を整えることが大切です。そのカギとなるのが、決済方法と配送方法。
まず決済方法には、以下のような選択肢があります。
- クレジットカード決済:世界中で使われている一般的な方法
- PayPalなどの電子決済:安全性が高く、海外でも人気
- 銀行振込:手数料は高いが、確実な方法
- 現地の決済サービス:例えば中国のAlipayやWeChat Pay
手数料も考慮に入れる必要がありますが、できるだけ多くの決済方法に対応すると、ユーザーの利便性が高まります。
次に、配送方法。
- 国際郵便:比較的安価だが、配送に時間がかかる
- 国際宅配便(DHL、FedExなど):迅速だが、高額
- 現地の配送業者との提携:現地のサービスを利用できる
配送方法を選ぶ際は、スピード、コスト、安全性のバランスを考えましょう。なお商品の追跡システムを導入すると、超親切。
ステップ4:多言語対応と現地サポート体制の構築
最も重要だけど大変なステップが、多言語対応と現地サポート体制の構築。ユーザーと直接やり取りする部分であり、ここでつまずくと、せっかく良い商品があっても国際問題に発展するかもしれません。
まず多言語対応について考えてみましょう。商品説明や利用規約、よくある質問など、サイト全体を現地の言語に翻訳する必要があります。しかしAIだけに頼るのは危険です。文化的な違いや微妙なニュアンスを伝えるには、やはり人の手によるものでないと危険。
あとはサポート体制です。ユーザーからの問い合わせに、迅速かつ丁寧に対応できる仕組みを作りましょう。例えば、
- チャットボット:簡単な質問に24時間対応
- メールサポート:詳細な質問や要望に対応
- 電話サポート:緊急の問題に対応
- ソーシャルメディアを活用したサポート:気軽に質問できる体制作り
時差の問題もあるので、24時間対応が難しい場合は可能な時間帯を明確に示しましょう。
最後に、現地の文化や習慣に合わせたコミュニケーションも大切です。例えばフレンドリーな対応でないと冷たく感じる国民性や、丁寧な言葉遣いでないとキレ出す国など。
こういった違いを理解し、適切に対応することで、ユーザーとの良好な関係を築いていきます。
まとめ
越境ECの定義、特徴、メリット・デメリット、始め方の4つのステップについて紹介しました。
- 越境ECの仕組みと特徴を理解する
- メリットとデメリットを十分に検討する
- 4つの準備ステップを着実に進める
これらのポイントを押さえることで、越境ECへの第一歩を踏み出せます。ただし、市場調査や言語対応など、準備にはしっかり時間をかけることが大切です。
焦らず、着実に準備を進めることで、成功への道が開けるはずです。